日本油料検定協会がJGAP認証機関に、「青果」「穀物」で審査開始、割引キャンペーンを実施
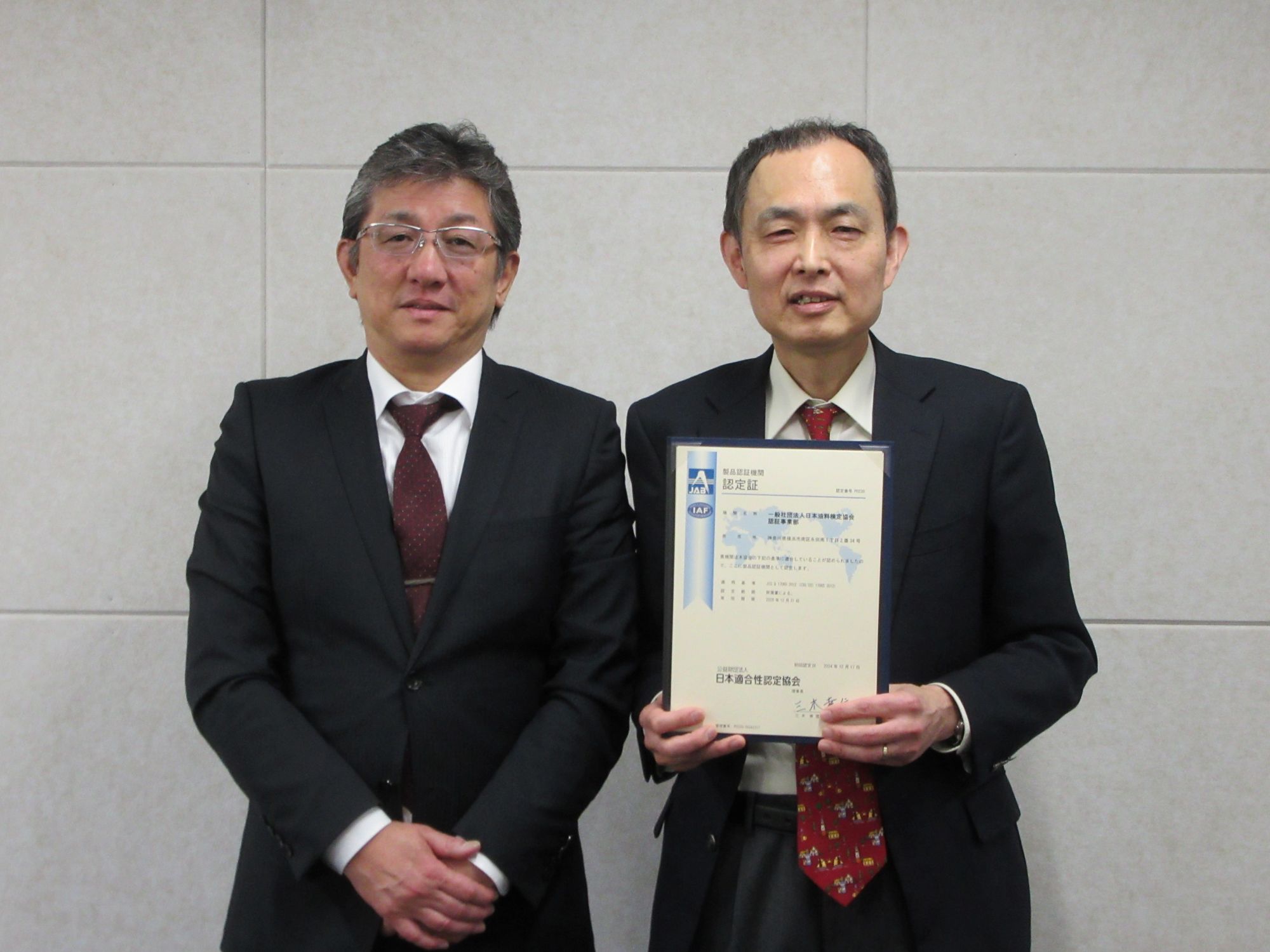
日本油料検定協会は昨年12月、日本適合性認定協会(JAB)から認定を取得し、国内6つ目のJGAP(ロゴ)認証機関となった。「青果物」と「穀物」の品目で個別審査「JGAP農産2022」を受け付けており、4月から2026年3月31日にかけて、JGAP認証取得応援キャンペーンを実施する。
2026年3月までに受審する先着5農場限定で、審査料金を割引して見積りを出すというもの。GAP(農業生産工程管理)とは、農業生産の各工程の実施、記録、点検、評価を行うことによる持続的な改善活動のことだ。農家が自ら実施する「GAPをする」段階と、GAPを実施していることが客観的に証明される「GAP認証をとる」段階がある。
GAP認証農産物に対しては、大手スーパーやコンビニ、食品メーカー、外食など、多くの企業から高い関心が寄せられており、消費者への認知が進めば、農家の認証取得へのインセンティブも高まる。氏原潤一会長と白砂尋士理事、認証事業部の早川泰弘副部長に新事業の狙いについて聞いた。
――JGAP認証機関の認定を目指した理由は

氏原 2023年3月からJGAP認定の取得を目指し始め、2024年12月17日に認証機関になった。当協会は油脂・油脂原料の検定、分析部門が立ち上がり70年以上経過した。
現状、検定関係と分析の2本しか事業の柱がなく、認証事業を新しい柱にしたいと考えた。既存事業で農作物に関係しているのでJGAPに焦点を当て、2年がかりで認証機関となった。当初は「茶」と「団体認証」も認定を取るつもりだったが、少しでも早く新規参入しようと、まずは「穀物」と「青果物」の認定を受けた。
目標としては来年度中に「茶」と「団体認証」も認定取得するための努力をしている。JGAP農産の認証機関は日本に5つあり、当協会は6つ目となった。専業ではないため障壁、課題はあるが、第3の柱に育て協会を支えるようにしたい。
◆日本の農業に貢献、第三者機関の強み生かして新しい事業分野にチャレンジ
――取得するに当たって大変だったことは
早川 証明機関として検定関係と分析を長く行ってきた。第三者機関として、事実証明するのは、認証も大きな違いはなく、親和性がある。一方、既存の検定、分析とは違う産業分野なので経験者が1人もいなかったことが大変だった。
認証業界の経験者は審査員含めて人がすぐ集まる状況ではない。認証機関をどう運営して事業として成り立たせるか、認定機関から認定を取得するノウハウもなかった。白砂理事以下、人材を5人集め、真っ白な状態から勉強した。日本GAP協会にも数えきれないくらい相談した。認証機関が増えるのは日本GAP協会にとっても望ましいと考える。
東京オリンピック・パラリンピックの調達コードにGAPが導入され、一時的なブームによって認証数が増えたが、現在は踊り場ないし微増で推移しており、オリパラの時期ほどは増えていない。新規顧客を新規の認証機関として増やしていくことが苦労している点だ。
――JGAPを選んだ理由と内容について
白砂 ASIAGAPとJGAPは日本GAP協会が運営主体で、認定を受けることで認証の仕事ができるようになる。JGAP認定取得の目的は2つある。
1つは、当協会は食の安全安心に貢献する目標の中で検定、分析を行ってきたが、扱っている農産物の多くは海外から日本に入ってきている。大豆などの農産物も数多く扱っているが、国産との関わりは薄かったので、日本の農業に貢献したいと考えた。
2つ目は、第三者機関の強みを生かして行う仕事として新しい事業分野にチャレンジすることだ。
GAPの場合、「青果物」、「穀物」、「茶」の品目がある。日本の農業は稲作が多いが、米や大豆の認証はそれほど多くない。半分が茶だ。GAPは良い農業に取り組んでいる農場に与えることになる。取るか取らないかは自由で、ビジネス上必要であれば取得することになる。
GAPパートナーである大手スーパーではGAP農産物の取扱いを推進しており、飲料メーカーでも、原料の仕入れ先として、GAP認証を取得した茶農園を求めている例もある。売場で青果物を取り扱う時にもGAP認証取得が要求されることもあるので、必要性があって取得する生産者が多い。
増えているのは「青果物」だ。スーパーで販売している野菜でJGAPを取得したものが増えてきた。
早川 JGAPなどは毎年認証審査が必要で、活動や適合性、合致する取り組みを維持する必要がある。認証を維持するのにコストもかかる。当協会は分析分野では大豆の遺伝子組換えの分析も行っている。検定では納豆など食品向け大豆の検量などで扱っているので、シナジーが出ればいいと考えている。
認証取得の動機付けが一番の課題だ。現状ではまだ十分インセンティブが見出せていない。野菜は高騰しているが、GAPすることの必要性や、どの程度の恩恵が受けられるかについて差別化が十分でないように感じる。普及が足踏みしている背景だ。GAPの付加価値として、消費者が対価を払い、農場に利益が還元されることが望ましい。
◆農業をマニュアル化して記録も取得、新たに従業しやすく、知名度向上へ地道な努力
――注力していくことは
早川 JGAP認証事業を軌道に乗せることが最優先課題だ。
白砂 日本の農業に貢献できるようにと言ったが、ASIAGAPやJGAPを含めて約7,700の農場が認証を取得している。県のGAPを含めると認証農家は4.4万ほどになるが、日本の農場を約100万とすると、数%にとどまる。JGAPなどの第三者による認証は1%にも満たない。
GAPの仕組みを導入すると、農場のやり方、農薬のまき方などを全てマニュアル化して記録も取る。それらのマニュアルや記録を見て農業をするので、新しく始める人も従業しやすい。日本の食料安全保障にとっても良い。新しい農業の担い手を育成することに貢献していきたい。
早川 青果物の売場でも、パッケージにJGAPと印刷されているものが目に付くようになってきたが、そのマークを見て購入されるという状況まではないように思う。無農薬や有機の方が消費者に馴染みはある。GAP認証が広まっていくと流れは変わってくるだろう。
GAPによる安全な野菜は必ずしも味に差が表れるものでないが、さまざまな対策をした上で農産物が流通に回っているということに、価値を見出せる世の中になればと思う。認証を通して日本の農業に貢献する。
――認定の継続は
早川 2024年12月に認定された。審査は厳密で厳しかった。毎年認定審査がある。審査機関としての仕組みをどう運営管理していくかは課題だ。今回取得できなかった「茶」や「団体認証」の取得に向けて認定審査を受ける必要もある。
――今後の活動方針を
白砂 他の審査機関はGAPだけでなくISOなどの認証も手掛けているところが多い。当協会は油脂業界、大豆業界では知られているが、認証においての知名度は低い。まずは知ってもらう必要がある。
JGAP認証審査は管理点と適合基準に基づいて審査するので、われわれだけが特別な審査、良い審査というわけではなく、他機関との差別化がしにくい。親切、丁寧な審査につとめ知名度を上げて、審査の申し込みをしてもらえるよう、地道な活動をしていく。
早川 第三者機関として食の安全安心に貢献する。
〈大豆油糧日報 4月4日付〉









