学校給食が届かない日が来る?物流危機で揺らぐ“当日納品”ルールの誤解

「朝3時に食材を揃え、5時に納品開始。受け取る調理員は5時半から出勤」–。ある卸業者が語る、学校給食を支える現場の過酷な実態だ。
いま、物流業界の人手不足と「2024年問題」の影響で、学校給食の当日納品が困難になる地域が全国的に増えている。パン、麺、牛乳、さらにはおかずやデザートまで、当日の配送が間に合わない、対応できないという声が続出している。
現場からの危機感:パンも牛乳も「製造できても届けられない」
先月行われたシンポジウムで、学校給食の流通に関わる製パン業者や卸業者、栄養学の専門家らが登壇し、現場の危機感と制度上の誤解、今後の対応策について語った。
登壇したのは、製パン業者で構成される全日本パン協同組合連合会の嶋内八郎氏。
「製造はできても、配送ができない地域が出てきている」と現場の厳しい状況を訴えた。給食向けのパン工場の廃業・撤退も相次ぎ、麺や牛乳でも同様の供給危機が発生しているという。
1都10県の卸企業で構成される関東給食会の平井昌一氏も、「これまでは何とか納品してきたが、それができなくなる時期がすぐそこまで来ている」と語る。
一部の自治体では、朝8~9時の1時間以内に納品を求める例や、1日に複数回納品が必要なケースもある。卸業者は営業社員まで配送に駆り出されるほどのひっ迫ぶりだ。
“当日納品が必須”は誤解だった
シンポジウムでファシリテーターを務めた、淑徳大学看護栄養学部客員教授の田中延子氏は、次のように語った。
「当日納品じゃないとダメだと思っている教育委員会や学校が多いが、実はそれ、法律には明記されていない」。
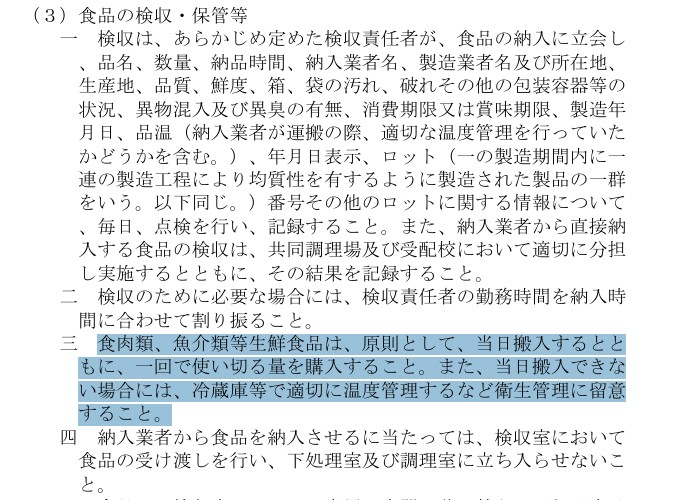
根拠となる「学校給食衛生管理基準」では、次のように記されている。
『食肉類、魚介類等生鮮食品は、原則として当日搬入すること。当日搬入できない場合には、冷蔵庫等で適切に温度管理するなど衛生管理に留意すること』
つまり、冷蔵冷凍庫で適切な温度管理ができれば、前日納品でも差し支えないというのが本来の制度の考え方だ。
冷蔵冷凍庫が「持続可能な給食」のカギに
田中氏は、「納品業者の前日納品を可能にすることで、調理員の労働環境も改善できる。早朝納品では栄養教諭らによる検品が困難で、アレルギー事故のリスクも高まる」と指摘。冷蔵冷凍庫や食品庫を一定容量整備することの重要性を訴えた。
また、「これまでは“買う側”が強い時代だったかもしれないが、これからは“買わせていただく”時代になる。物が届かない未来を避けるためにも、教育委員会や学校側も受け入れ態勢を見直す必要がある」と呼びかけた。
問われる「仕組みの柔軟性」
いま学校給食の現場で起きていることは、単なる物流の話ではない。
それは、長年“常識”として運用されてきたルールの見直しが求められているということでもある。
「当日納品が当たり前」という思い込みこそが、いま現場を苦しめている。
給食を支えるすべての人のために、“常識”の方を見直す時が来ている。









